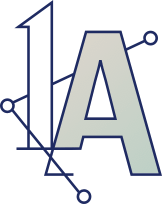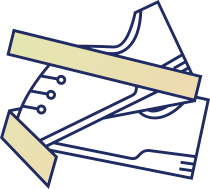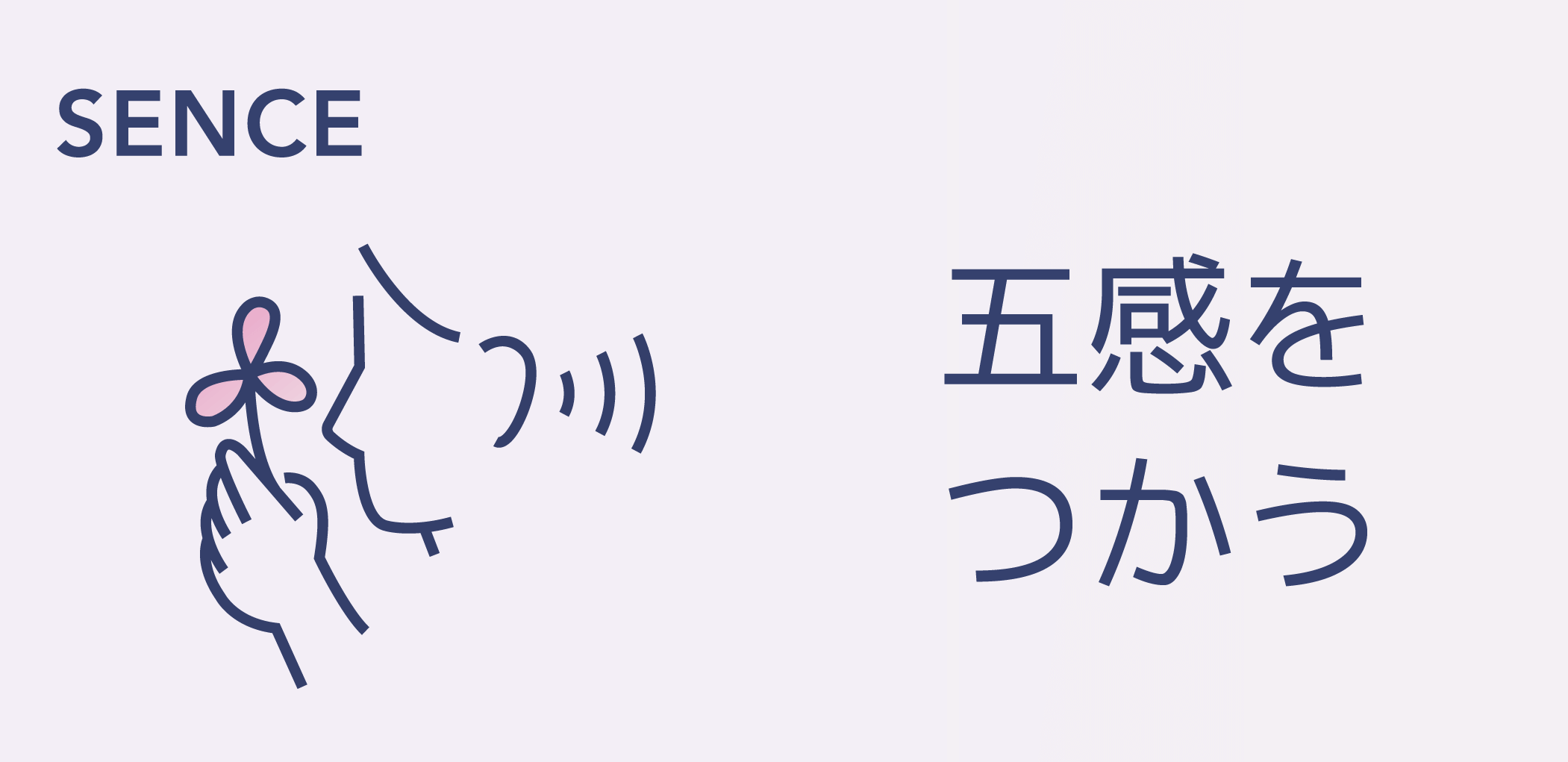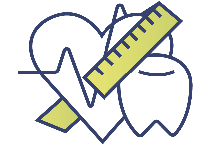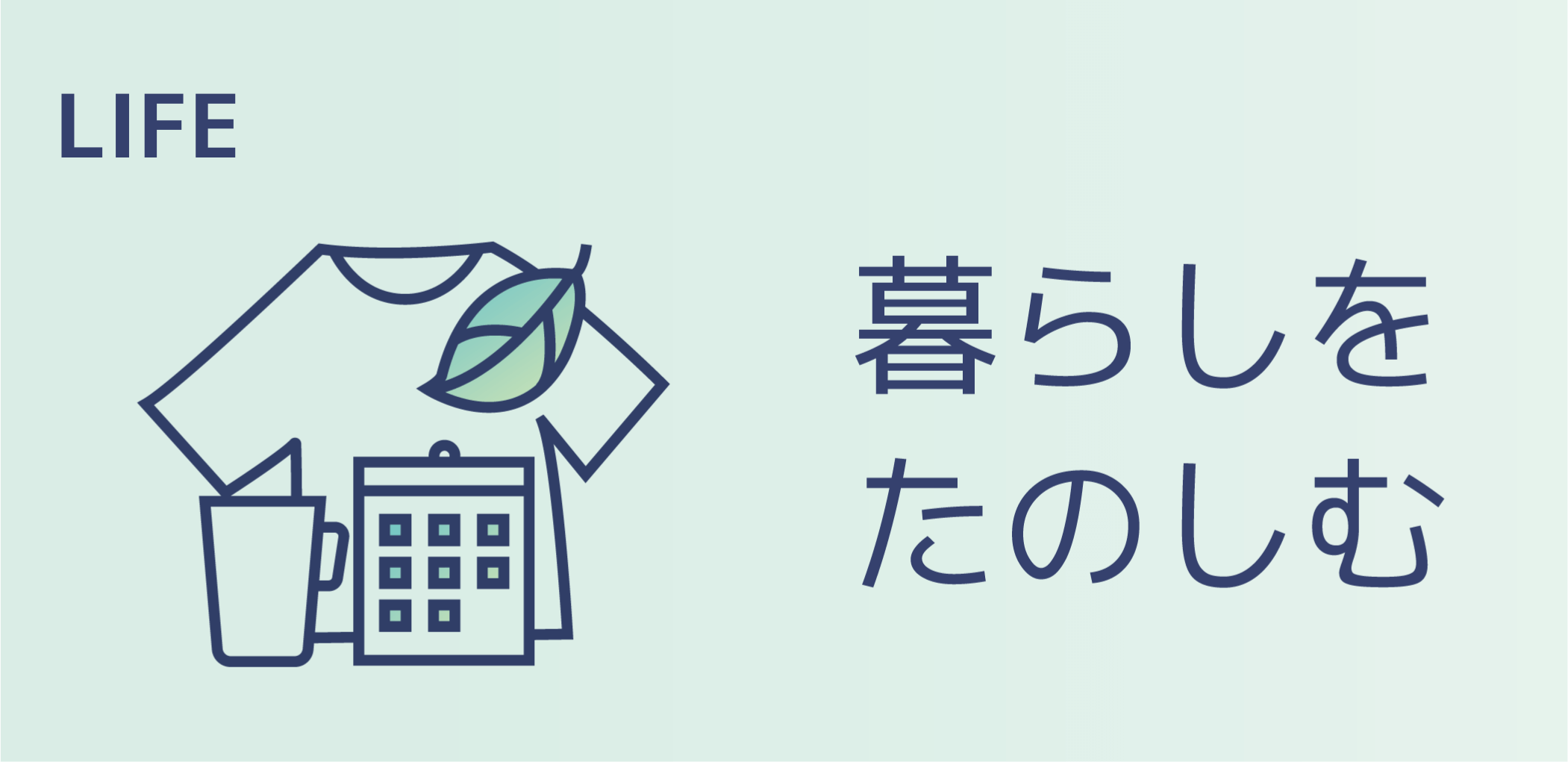成長、発達、認知――。教育関係の記事ではあたりまえのように使われる言葉ですが、その厳密な意味となると答えられない人も多いでしょう。お話を聞いたのは、『しまじろうのわお!』(テレビ東京)などの幼児教育番組や幼児向け教材の監修を行っている、静岡大学情報学部客員教授の沢井佳子先生。それらの言葉の意味に加えて、幼児教育の世界で流行語となっている「非認知能力(非認知的スキル)」という言葉がはらむ問題についても持論を語ってくれました。
構成/岩川悟 取材・文/清家茂樹 写真/石塚雅人(インタビューカットのみ)
目次
成長、発達、認知という言葉の意味とは?
成長、発達、認知という言葉のうち、その意味合いからも混同されるのが成長と発達ではないでしょうか。子どもの成長、発達といった場合、一般の会話においては大きなちがいはありません。でも、アカデミックな意味でいうと両者にはちがいがあります。
「成長」とは、「数値」でわかる身体の量的な変化です。つまり、子どもでいえば身長が伸びたり体重が増えたりした場合に、「成長した」というのです。そして、「発達」とは「働き」や「質」に焦点をあてた心身の変化です。たとえば、「子どもが手指で柔らかいものを上手につまめるようになる」という動作の「器用さ」の変化や、そして「頭のなかで言葉や数や論理を理解する」というような、見た目だけではわからない心理的変化も「発達」に含まれます。
この発達の過程において、生涯にわたってドラマチックな変化を見せるのが「認知の発達」です。「認知」とはごく簡単にいえば「ものごとがわかる」ということです。一般に認知能力というと、文字を書く、計算する……といった「学力」と同じ意味だと、非常に狭い意味でとらえられがちです。しかし、認知は人間のあらゆる「知覚」「運動」「学習」「判断」「記憶」などに関わります。
たとえば、生活習慣の獲得。子どもが服を上手に着られるようになったなら、そこには、方向や位置関係がわかる……という空間認知や、見て触った情報をもとに動作を実行するという認知の発達がみられるのです。友だちとの付き合いにおいても、表情を認知し、視点を動かして相手の気持ちを察し、出来事のつながりから因果関係を推理し、行動の社会的な結果を予測して意思決定をする……といった認知の過程がたくさん含まれているのです。生活習慣から社会生活、おしゃべりから数の理解、砂場の遊びからスポーツの試合まで、子どもの頭のなかでは認知的な営みが忙しく繰り広げられているのです。

子どもの教育から少し話はそれますが、この「認知」に関する言葉で、個人的に残念に思っているのが、2004年末に日本で「痴呆症」に代わるものとして「認知症」という名称が採用されたということです。「認知症」という名前は、そのままの意味でとらえると、「わかる病気」ということになってしまいます。当時、厚労省が行ったアンケートでも、ほとんどの有識者が「認知障がいという名称が適切」と答えていました。
「認知」を「歩行」に置き換えて考えてみましょう。歩行器で歩く人も、車椅子を使う人も「歩行障がい」があるわけです。が、それを「歩行症」と呼んだらおかしいですよね。「うまく認知できないこと」は、本来なら「認知障がい」と呼びたいところです。「でも、厚労省側が『少しでも字数が少ないほうがいい」と判断して『認知症』という言葉に決まったんですよ」と、その検討会の座長を務めた医師の長谷川和夫先生から、直接お聞きしたことがあります。
こうして「認知症」という名称が生まれて15年がたったいま、「うちのおじいちゃん、『ニンチ』になっちゃって……」といったふうに、ずさんに略されて使われるのを耳にします。認知という言葉が真逆の意味で使われるのです。
わたしは「みんなの認知症情報学会」で、認知症や発達障がいの当事者の方々のお話を聞く機会があるのですが、そのなかのひとりの女性が「わたし自身の認知の特徴について正確に説明しようとしても、ニンチという言葉は、得体の知れない深海魚か怪物のように思われ、人の誤解を解くのは大変です」とお話しくださったことが忘れられません。「認知症」のように、名前と意味の関係をあいまいにした言葉は、誤解に悩む人を増やしてしまうのです。

「社会情動的能力」を「非認知能力」と呼ぶべきではない
「認知」の意味への誤解を広げている名称がもうひとつあります。現在の教育界で頻繁に聞かれる「非認知能力(非認知的スキル)」がそれです。米国の経済学者のヘックマン(J.J.Heckman)の著書『子どもたちに公平なチャンスを与える(”Giving Kids a Fair Chance”)』邦訳『幼児教育の経済学』(東洋経済新報社)のなかに「非認知能力」は登場します。
ヘックマンは米国の公教育が、子どもたちを到達度テストの点数で評価し、「学力優位の教育に偏っている現状」を批判しています。多くの人が社会で成功し、経済格差を解消するためにも、到達度テスト(認知テスト)では測れない、意欲や長期計画を実行する能力、他人と協働するのに必要な社会的・感情的制御という「非認知能力」を伸ばす教育が重要である。そして幼児期こそ「非認知能力」を育む最適期なので、幼児教育にかかる費用を、社会が家庭へ「事前に分配」すれば、効率的に社会的格差が解消される――。と、幼児教育への社会的投資を促しました。
わたしは、この結論には賛成です。経済階層や家庭環境のちがいにかかわらず、どの子どもにも適切な幼児教育の機会が与えられるように社会システムを作ること。そして、学業のみならず、社会性や情動コントロールの能力を育む「幅広い領域の教育」の恩恵をすべての子どもが得られるように、社会が幼児期にお金と手間をかければ、子どもが年を取るまで望ましい効果が得られ、人生も社会全体も豊かになる……というヴィジョン。これは、わたしが30年以上前から、テレビ幼児教育番組のコンテンツ開発の仕事をしながら思い描いてきた理想と重なります。

しかしながら問題は、社会性や情動コントロールの能力を「非・認知能力」と名づけ、学業に関わる能力だけを「認知能力」と名づけたことでした。わたしは、その意味する「事柄」ではなく、「名称」を問題視しています。
ヘックマンは当初、「(研究者が)数値で量的に認知しやすい能力」と、「(研究者が)数値では認知しにくい能力」とを区別するつもりで、認知能力と非認知能力と命名したようですが、そんな名称では「子どもの頭のなかの認知能力」と区別がつきませんし、実際、混同されています。
社会性や情動コントロールの能力のなかには膨大な認知過程があるにもかかわらず、それを「非認知」と呼べば、一般の人は「人付き合いや、我慢ができることなどに、認知は入っていないのだな」と誤ってとらえてしまうでしょう。そもそも、「非(Non-)」が頭について、「認知『じゃないもの』が大事だ」……という造語の仕方が誤解のもとです。大事な事柄は、否定ではなく肯定で、端的に表現すべきでした。
ヘックマンは学業の能力(彼のいう認知能力)と社会情動性の能力(彼のいう非認知能力)の両立を重視したはずですが、教育者の間では「非認知能力」あるいは「非認知スキル(Non-cognitive skills)」という名称のみが流行語になり、両者のバランスは崩れていきました。さらに「非」という接頭辞が、続く「認知能力」を排除するか、または時間的に後回しにする解釈へと迷走させています。
「<我慢ができて、友だちと仲良く協力し合い、自分の感情をコントロールする力>は非認知能力であり、これが育ったあとに認知能力を伸ばせばよいのです」と、幼児教育の現場で語られるのを聞きましたが、これは、ふたつの能力を同時に重視するヘックマンの論旨に反します。また、赤ちゃんのときからの「顔や声のパタンを見わける認知能力」がベースにあってこそ、特定の大人への愛着が深まり、観察と模倣の学習も進み、社会情動的能力が発達するのだという、心理学の知見ともかみ合いません。学術的な知見と「つじつま」が合わないまま、「非認知能力」という名称は、一般の人々の「認知」への理解をゆがめているのです。

幼児期にこそ「認識の枠組み」を与えたい
2011年の東日本大震災のとき、米国の『TIME』誌は、被災者の写真とともに「“Gaman”=ガマン」という言葉を「日本人独特の精神性」を象徴するものとして紹介していました。米国人のヘックマンが想定した「忍耐力や情動の抑制のレベル」をはるかに越えるマグニチュードの「被災者の我慢」に、米国のジャーナリストは驚いたのです。
幼児教育の現場はもちろん、日常の現実やアニメでも「我慢強い子」のモデルを多く目にする日本は、「他者と協働するための社会性」への期待が重過ぎるほどです。ですから「非認知能力」と呼ばれる「社会・情動性」の教育の旗を振らなくても、日本の幼児教育の先生方はすでにそれをたっぷりと教育なさっていると思います。が、近年の「非認知能力」という流行語の副作用として「認知能力」が狭く解釈され、「文字や数を学ぶ認知能力は、小学校から伸ばす」とみなされ、幼児の幅広い認知能力が論じにくくなったのは問題です。
他方、小学校はといえば、STEAM教育(科学、技術、工学、芸術、数学)を代表するプログラミング教育に加えて、英語の教科化で忙しく、6歳からの知識学習はどんどん増やされています。6歳を境に幼児教育と小学校の教育の内容には、崖のようなギャップがあります。それを不安に思う親は、非認知能力重視をうたう幼稚園に子どもを通わせつつ、さらに国語、算数、英語の「学業の先取り」を助ける塾へも通わせ、ダブルスクールの行き来で親子はヘトヘト。楽しいはずの幼児期がこのような疲労感で終わっては、「意欲」を育むどころではありません。

そこで思い出すのは、わたしが2004年にハンガリーの保育園を訪ねたときの驚きです。保育士が「さあ、論理で遊びましょう!」と、3歳から6歳の子どもたちを集め、おもちゃや絵本、ボールなどを使って、仲間わけの論理遊びをはじめました。子どもたちは、異年齢同士で相談しながら、おもちゃを選び、ボールを転がして「考える遊び」を楽しんでいたのです。「考えること」は運動であり、友だちとのコミュニケーションであり、答えを探すための忍耐も遊びの内でした。ブダペストの明るい教室には、「子どもの思考」への洞察と、「考える遊び」を開発する技術があり、芸術的なバランスがあることに、わたしは心打たれました。
ブダペストの小学校も見学しましたが、幼児教育から滑らかにつながり、校長は「幼児から児童への認知発達を考え、自分で論理的に考えられるように、遊びや学びを開発しているんですよ」とお話しくださいました。論理、社会性、物語、数学、運動、音楽などが、一体となった教育は、面白い幼児教育番組を見ているような印象を残しました。
1973年にはじまった幼児教育番組『ひらけ!ポンキッキ』(フジテレビ)は、ガチャピンとムックが有名ですが、東 洋、永野重史、新田倫義、藤永 保という4人の発達心理学者が監修して、幼児期の認知発達を支援する目的でつくられました。わたしは1984年から1988年まで心理学スタッフとして制作に携わりました。
放送がはじまった頃は、批判の電話がたくさんあったそうです。「幼児期はココロを育てる情操教育が重要なのに、『ポンキッキ』は知識の詰め込みの早期教育でけしからん」という批判です。「知性と情意性、どっちを重視するのか?」という、能力を分割する議論は、むかしもいまも変わらず繰り返されるんですね。『ポンキッキ』の監修者は、「幼児が主体的に情報を処理する能力を育て……質の良い知的構造の形成と深化を目指す」という理念を掲げ、論理概念すらも面白いアニメで見せ、社会性や情動性をテーマにした歌やダンスも開発しました。
いま、わたしは『しまじろうのわお!』(テレビ東京)という幼児教育番組の監修者として、ピーマンの悲しみの理解から、転んでも立ち上がる意欲の歌、ジュースの量を比べる遊びまで、幼児の生活全体を対象に、『認識の枠組み』を与える映像を開発しようと、制作仲間と議論を重ねています。
ハンガリーの「社会的な論理遊び」、そして「生活のなかで考える面白さ」を伝える『ポンキッキ』、こうした「認知と情意性の発達を丸ごと支援する教育」を、いろいろなメディアで増やしたいものです。大人のかたも、子ども時代の記憶を思い出して、「3歳のわたしが面白かったことは? 大好きな人のなにを真似たのかな?」とご自分の発達を振り返ってみませんか? 「認知=ものごとがわかること」について考えはじめると、高齢者になるという発達も面白くなるように思います。

■ 静岡大学情報学部客員教授・沢井佳子先生 インタビュー一覧
第1回:“○歳だからこれができないとダメ!”その思い込みから親を解放する「発達心理学」入門
第2回:幼い子どもの言葉が格段に豊かになる、親から子への「実況中継」という方法
第3回:「10まで言えるのに、5個が数えられない」? 未就学児への“数”と“時間”の教え方
第4回:「非認知能力」という名称の流行が生んでしまった“誤解”と“困った副作用”
【プロフィール】
沢井佳子(さわい・よしこ SAWAI, Yoshiko)
1959年生まれ、東京都出身。チャイルド・ラボ所長、静岡大学情報学部客員教授。認知発達支援と視聴覚教育メディア設計を専門とする。学習院大学文学部心理学科卒業。お茶の水女子大学大学院人文科学研究科修士課程修了。同大学院人間文化研究科博士課程単位取得退学。専攻は発達心理学。幼児教育番組『ひらけ! ポンキッキ』(フジテレビ)の心理学スタッフ、文教大学人間科学部講師などを経て現職。他に、日本こども成育協会理事、人工知能学会「コモンセンス知識と情動研究会」幹事、日本子ども学会常任理事などを務める。幼児教育シリーズ『こどもちゃれんじ』(ベネッセコーポレーション)の「考える力」プログラム監修、幼児教育番組『しまじろうのわお!』(テレビ東京系列/2016年国際エミー賞子ども番組部門ノミネート、2019年アジアテレビ賞受賞)の監修など、多様なメディアを用いた幼児向け教材やテレビ番組の制作におけるコンテンツ開発に携わっている。
【ライタープロフィール】
清家茂樹(せいけ・しげき)
1975年生まれ、愛媛県出身。出版社勤務を経て2012年に独立し、編集プロダクション・株式会社ESSを設立。ジャンルを問わずさまざまな雑誌・書籍の編集に携わる。