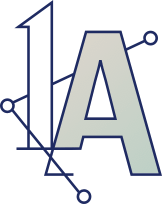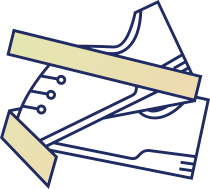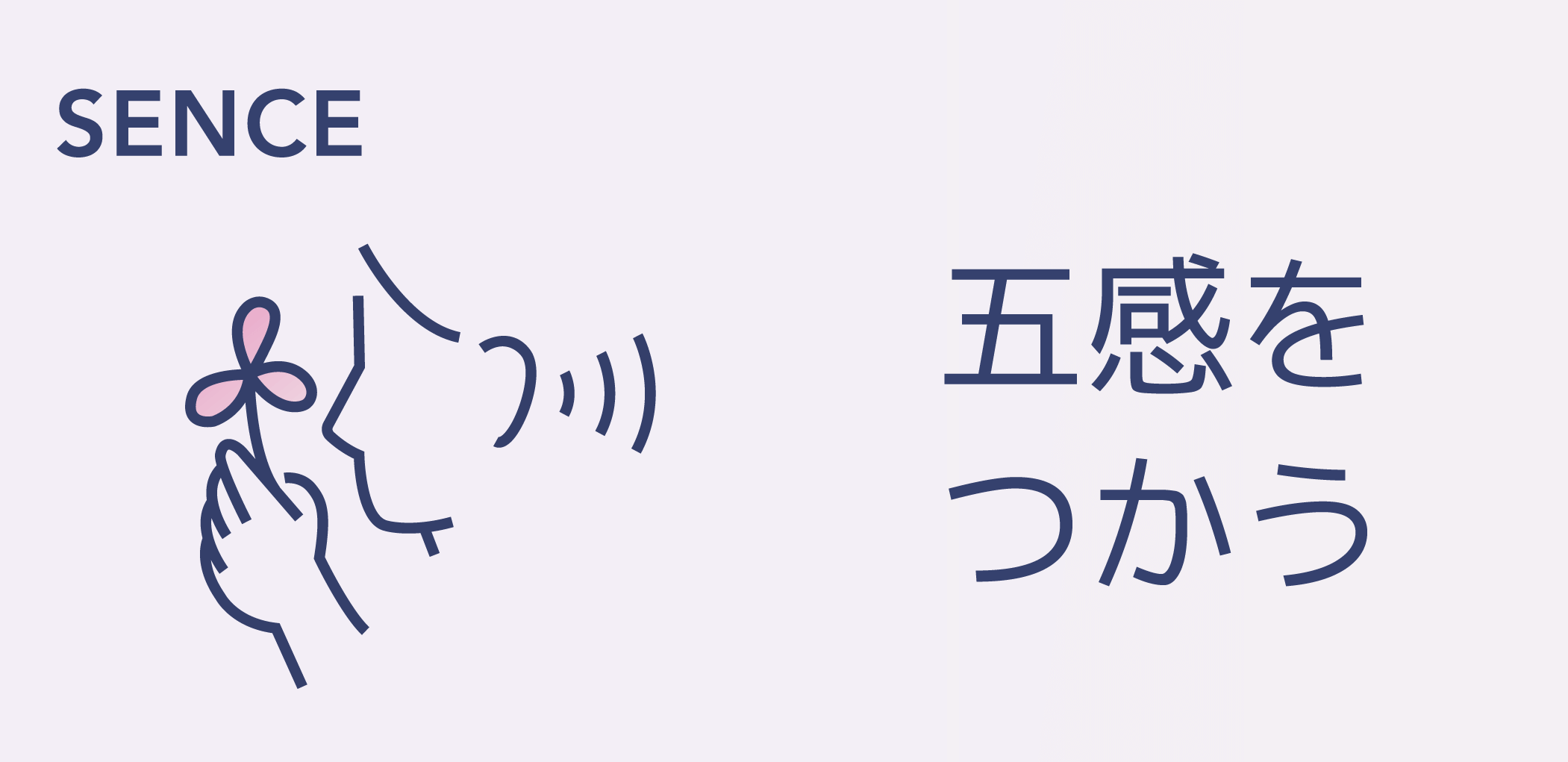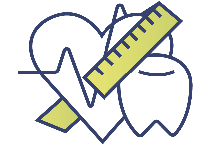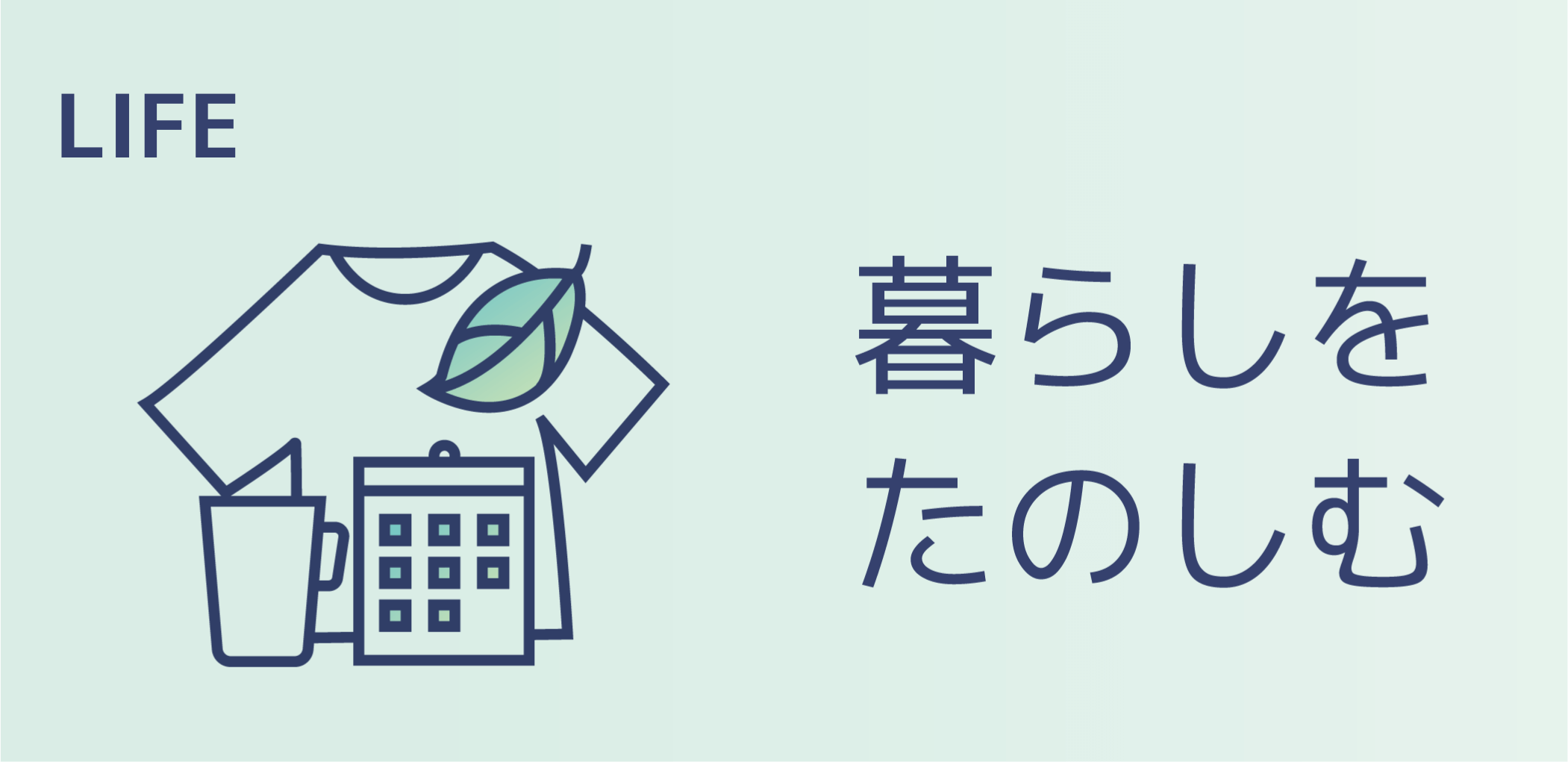(この記事はアフィリエイトを含みます)
2010年に設立された「一般社団法人TOKYO PLAY」。「すべての子どもが豊かに遊べる東京」をコンセプトに、東京でさまざまな「遊び」を仕掛けています。今回取材を受けてくださった代表理事・嶋村仁志さんは「プレーパーク」のエキスパート。TOKYO PLAYの活動、そして、「プレーパーク」とはどんなものなのかを教えてもらいました。
構成/岩川悟 取材・文/清家茂樹(ESS) 写真/玉井美世子(インタビューカットのみ)
目次
主な活動は「遊ぶことの大切さ」を伝える啓発
「TOKYO PLAY」は、もともとわたしが2007年に立ちあげた「子どもの遊びと大人の役割研究会」というものがベースとなっています。それを発展解消させるかたちで、2010年に設立しました。
主な活動は、「遊ぶことの大切さ」を伝えていく啓発にあります。いま、いちばん力を入れているものが、都内のあちこちで仕掛けている「とうきょうご近所みちあそびプロジェクト」。地元地域に暮らす人たちが町会や商店街と協力し、使用許可を取った道路で多世代の人が楽しみ、交流する場所をつくることを支援するというものです。
普段ならお互いにすれちがうだけの関係の人たちが、「遊ぶ」というキーワードによって交流する。近所の子どもたちの育ちの場、世代を超えた交流の場にしたいと考えています。
ただこれは、むかしであればどの地域でもあたりまえにできていたことかもしれません。でも、いまはなかなか難しい。車の交通量は増え、社会の少子高齢化が進むなかで静かに暮らしたい人たちも増えています。その結果、住民同士のコミュニケーションは、都会に限らず、田舎でもなくなりつつあります。
そうした傾向が影響しているせいもあるのか、子どもが道で危ないことやご近所に迷惑がかかることをしているのをそばで見ているにもかかわらず、注意できない親や、夜中まで家の前でバーベキューをして、注意されても「え? なにが悪いの?」といわゆる逆ギレするような人もいます。

「将来の大人」をきちんと育てなければならない
こういう人たちは、「道路族」として呼ばれることもあるようですが、その背景として、子どもの頃に近所の人にかわいがられたり、逆に迷惑をかけて怒られたりしたような、ご近所の他人とのコミュニケーション経験がないまま大人になってしまったのかもしれません。本来、家のすぐ近くの環境というのは学びの宝庫でした。
そこで遊んでかわいがられたり怒られたりして学んだ経験があり、近所に断りを入れる、気を使うといったあたりまえのことができれば、本来はこんな問題は起きませんよね。せっかくいい大学、いい会社に入ったにもかかわらず、近所の人たちと必要最低限のやり取りもできないような大人を再生産しないためにも、家のすぐ近くの環境の使い方を見直さないといけない時代になってきているのです。わたしたちのプロジェクトが公園ではなくご近所の道に着目していることには、そうした理由があります。
そういう意味では、「将来の大人」をきちんと育てなければならないということになる。2060年の日本では、子どもと大人の数の割合が1対9.96になるという試算があります。ひとりの子どもを約10人の大人たちがどんな目線で見るのか、それが重要です。
子どものことを、邪魔なものであったり「自分には関係ない」と思ったり、あるいは子ども教育の専門家などが自分のサービスの「お客」として見る。そういうものばかりだとしたら、その社会では子どもをきちんと育てることができないのではないでしょうか。そうではない、ご近所できちんと子どもを育てられる環境を確保したいのです。

デンマーク発祥の「冒険遊び場」
わたしが子どもにとっての遊びの役割に興味を持ったのは、「冒険遊び場」との出会いがきっかけでした。冒険遊び場が生まれたのはまだ第二次世界大戦中だった1940年代のデンマーク。コペンハーゲン郊外で住宅地を造成しているなか、新しい公園をつくることになった。
その都市計画に関わっていたソーレンセン氏は、大風の日に倒れた木に子どもたちが群がって遊んでいる姿を見たことがありました。また、廃材置き場にも面白さを見出していたそう。その構想を生かして生まれた新しい公園が、「廃材遊び場(Junk Playground)」です。
そして、第二次世界大戦が終わったイギリスのロンドンでは、がれきのなかで子どもたちが遊んでいました。「大人よりも早く子どもたちはがれきのなかで復興をはじめている」と言われるなか、今度はイギリスの都市計画家、アレン・オブ・ハートウッド氏がデンマークの廃材遊び場を見て、「これだ!」と思ったのだそうです。
ただ、そのままの名称ではイメージがあまり良くない。そこで、当時、子ども教育に熱心だったイギリス王室関係者が「いま、子どもたちが必要としているのは『冒険』だ」として、「冒険遊び場(Adventure Playground)」と名前を変えてイギリスに広まることになりました。現在、イギリスでは250カ所くらい、ドイツでは400カ所くらいの冒険遊び場があります。これが、日本では「プレーパーク」という名称でも広まっているのです。

写真提供:嶋村仁志
子どもの発想と想像力によって変化する遊び場
プレーパークは、一般的な公園とはまったくちがうものです。大人が完成品として用意した遊び方も決まっている遊具やプログラムのようなものはありません。あるのはいわゆるネコ車やのこぎり、金づち、シャベルといった道具に木、土、水、火など、それからさまざまなガラクタです。
それを、子どもたちが「やってみたい」と思ったふうに使って遊ぶ。大人が遊び方を指示するなんてことはありません。子どもの発想と想像力によってつねに変化していく遊び場というわけです。もちろん、置かれているガラクタもつねに変わっていきます。たとえば、ある日突然、古タイヤが置かれるといった具合です。

写真提供:嶋村仁志
先日わたしが視察したロンドンの冒険遊び場では、ロンドンオリンピックのときに公園で使われ、廃棄予定だった大きな滑り台が設置されていましたね。こういうふうに、海外ではけっこう大規模なものもあります。
ドイツには、プレーパークで働くプレイワーカーの指導を受ければ、子どもたちだけで高さ4メートルまでの建物をつくってもいいというルールがあるところも。中高生くらいになると、自分たちでスケボー用のランプをつくったという例もありますよ。

写真提供:嶋村仁志
当然、危険はつきものです。ただ、子どもたちは小さなけがから学ぶことも多い。ですから、危険をどう判断するかが重要です。冒険遊び場では、子どもの目が届かないような本当の意味での危険は排除し、大事故につながらないための介入はします。でも、チャレンジという意味での危険は残すことを大切にしています。
なぜなら、それらは子どもたちの「心の冒険」だからです。生活のなかでドキドキ、ワクワクすることが、子どもにとってなによりも大きな学びになるのです。

『子どもの放課後にかかわる人のQ&A50 子どもの力になるプレイワーク実践』
嶋村仁志 他 著/学文社(2017)

■ TOKYO PLAY代表理事・嶋村仁志さん インタビュー一覧
第1回:遊具なし、プログラムなし。異例だらけの“ガラクタ遊び”が欧州で大人気の理由
第2回:大切にしたい遊びの“リスク”。子どものチャレンジを支える遊びのルールとは?
第3回:子どもの工作が“失敗作”でも、親はアドバイスしてはいけない
第4回:中高生では遅い。子どもが体験すべき「小さな危険」と「小さないたずら」
【プロフィール】
嶋村仁志(しまむら・ひとし)
1968年8月6日生まれ、東京都出身。子ども時代は野球と自転車と缶けりざんまいの日々を送る。英国・リーズ・メトロポリタン大学社会健康学部プレイワーク学科高等教育課程修了。1996年に羽根木プレーパークの常駐プレーリーダー職に就いて以降、プレイワーカーとして川崎市子ども夢パーク、プレーパークむさしのなど各地の冒険遊び場のスタッフを歴任。その後フリーランスとなり、国内外の冒険遊び場づくりをサポートしながら、研修や講演会をおこなう。2010年、「すべての子どもが豊かに遊べる東京」をコンセプトにTOKYO PLAYを設立。2005年から2011年までIPA(子どもの遊ぶ権利のための国際協会)東アジア・太平洋地域副代表を務め、現在はTOKYO PLAY代表理事、日本冒険遊び場づくり協会理事、大妻女子大学非常勤講師。
【ライタープロフィール】
清家茂樹(せいけ・しげき)
1975年生まれ、愛媛県出身。出版社勤務を経て2012年に独立し、編集プロダクション・株式会社ESSを設立。ジャンルを問わずさまざまな雑誌・書籍の編集に携わる。