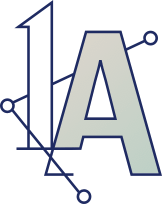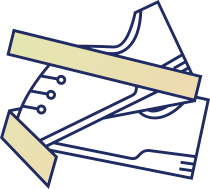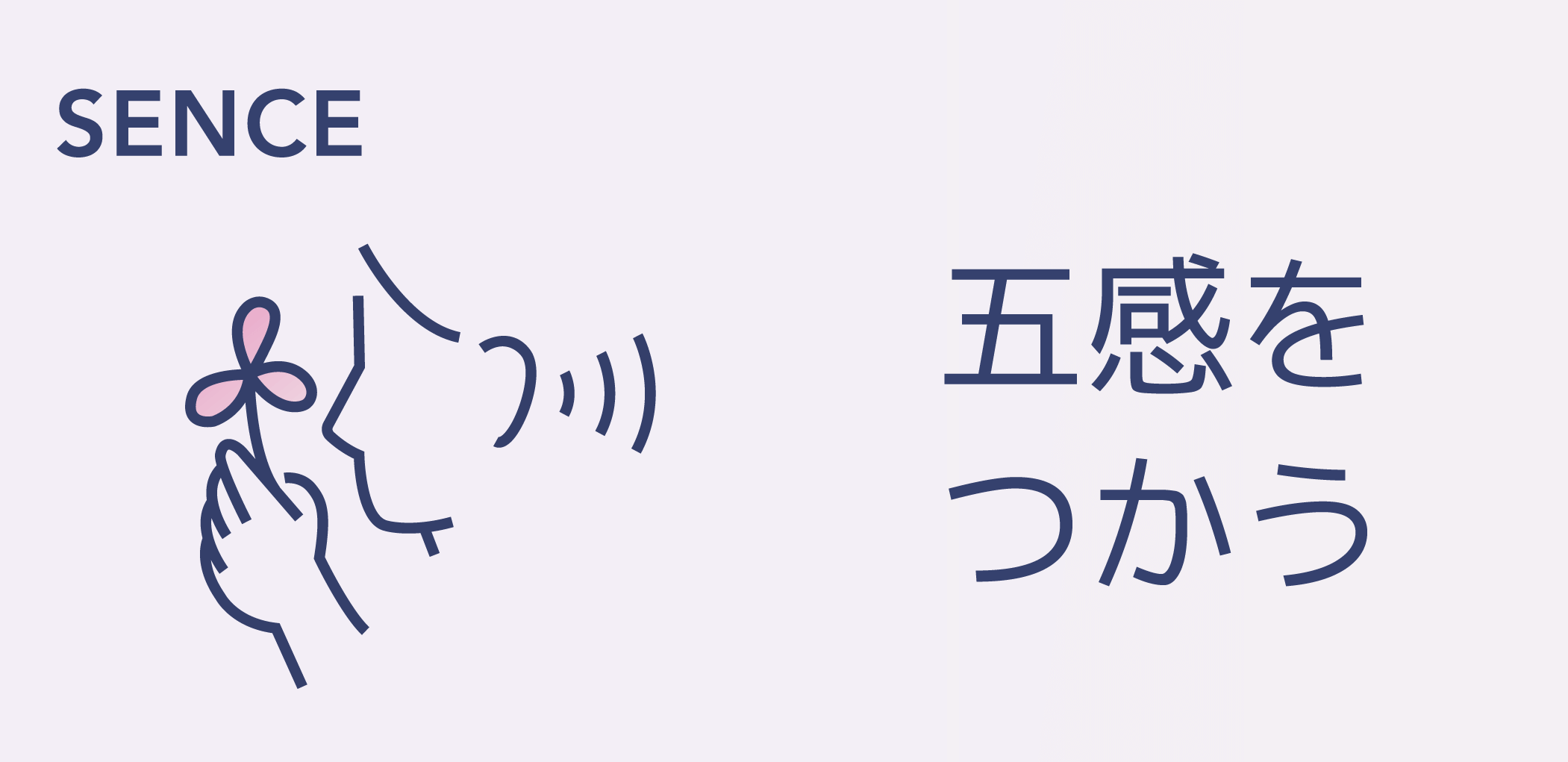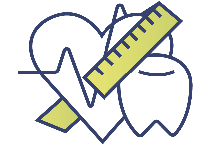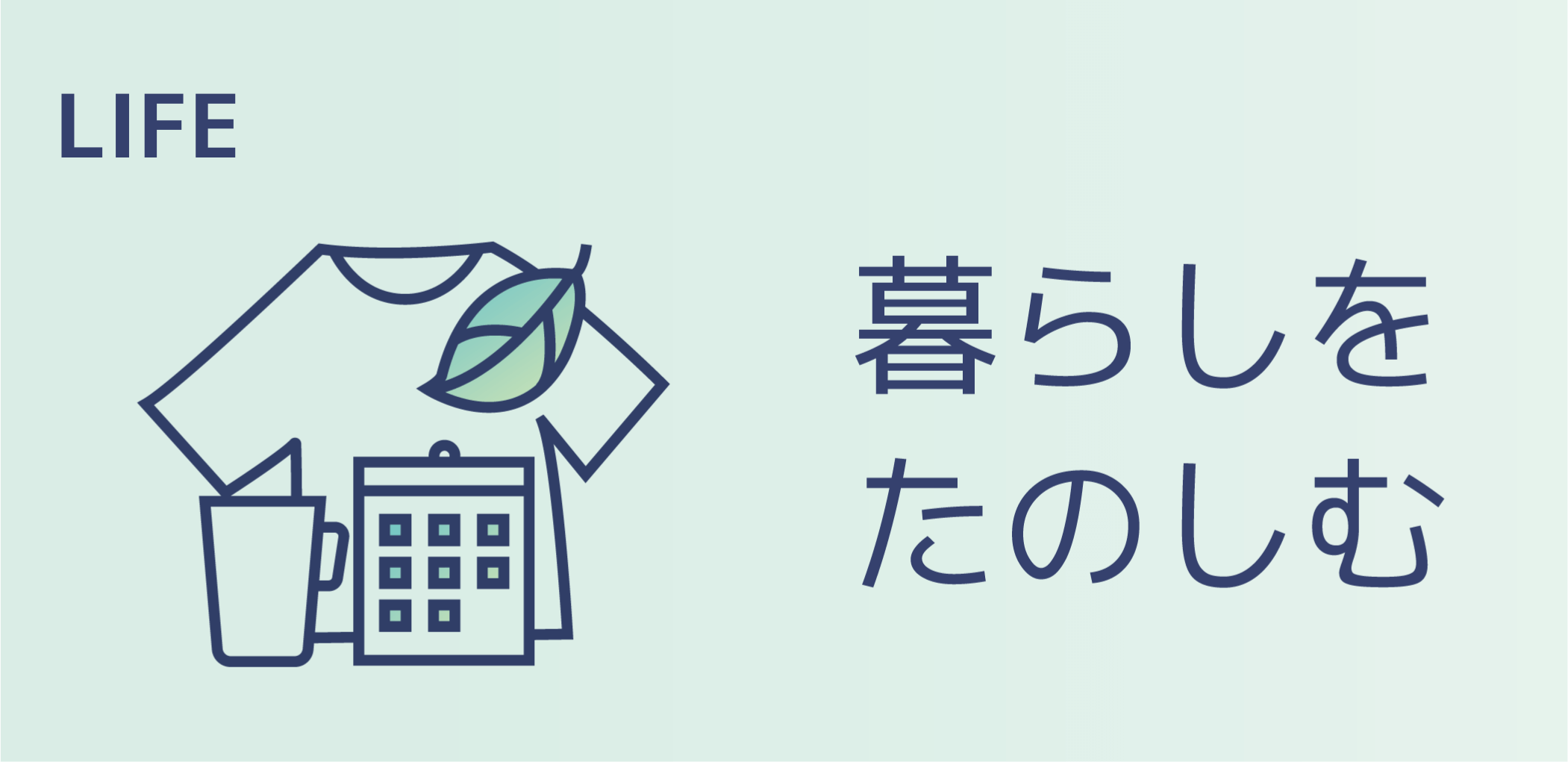(この記事はAmazonアフィリエイトを含みます)
都会では子どもたちの遊ぶ場がどんどん減っているなか、さまざまな「遊び」をしかけている人たちがいます。それが、2010年に設立された「一般社団法人TOKYO PLAY」。活動の主な目的は、子どものために遊びを大事にする大人を増やすこと。お話を伺った代表理事・嶋村仁志さんは「プレーパーク」のエキスパートでもあります。プレーパークで遊ぶことが、子どもにどんな影響を与えるのでしょうか。
構成/岩川悟 取材・文/清家茂樹(ESS) 写真/玉井美世子(インタビューカットのみ)
冒頭写真提供:嶋村仁志
目次
モットーは「自分の責任で自由に遊ぶ」
デンマークで生まれ、イギリスで発展した冒険遊び場(インタビュー第1回参照)は、日本でも「プレーパーク」という名称で徐々に広がりつつあります。公園の一角や河川敷、里山など私有地を使わせてもらって不定期で設置する、あるいは月に1回、年に数回といった具合に定期的に設置するものについてはだいたい400カ所くらい。常設のものは20〜30カ所といったところでしょうか。
国内初の常設プレーパークが、東京・世田谷の羽根木プレーパークです。開園は1979年。そこで、プレーパークについての重要な考え方が根づくきっかけとなった出来事が起こりました。開園間もない羽根木プレーパークで子どもが怪我をしてしまった。運営者と地域住民の話し合いのなか、ルールをきちんと看板にして掲げようという話になりました。
当初は「自由に遊ぶ」ということだけを掲げるという案もありました。でも、本当に自由に遊ばせるためには、大人から子どもに「責任」を返してあげないとならないのです。大人の世界でもそうですが、なにかにチャレンジするというときに「失敗したら責任は誰が取るの?」なんて言われたら、それは「チャレンジするな」と言われていることとほとんど同じですよね。
そうなると、チャレンジしたい、「やってみたい」という気持ちが奪われてしまうのです。であるなら、子どもに責任を返していこうという表現をした方がいい。そういう経緯があり、「自分の責任で自由に遊ぶ」という看板を掲げました。これこそ、プレーパークのモットーです。

自由な遊びで「責任」を学んだ子どもたち
「責任」についての話をもう少ししましょう。あるプレーパークによく遊びに来ていた小学生の兄弟が泥だらけになって帰ったときのこと。お母さんが帰宅したら、ふたりで仲良くお風呂に入っていたのだそう。しかも、洗濯機には脱いだ服がちゃんと入っている。いつもはお風呂にはなかなか入らないし、服は脱ぎっぱなし。でも、このときはちがった。兄弟は、泥だらけになって服を汚してしまったことに対して、小学生なりに「責任」を感じたようだということを、次の日になってお母さんが教えに来てくれたことがあります。
別のプレーパークでは、ちょっとした怪我をした子どもがいた。「念のため、おうちの人に連絡しようか?」と聞くと、「嫌だ」と言う。これはよくあるパターンなんです。怒られたくないとか、「もうプレーパークに行っては駄目」と言われるかもしれないとか、子どもはそう思うんですね。でも、あまりにも頑なに拒絶するので、その子に理由を聞くと、「僕がやりたいことをやって怪我をしたのに、プレーパークの人に謝らせたくない」と言うではありませんか。ちょっとびっくりしましたね(笑)。
自分のやったことを人のせいにせず自分で責任を持つというのは、あたりまえですが、大人になったときにすごく大事な価値観ですよね。でも、それは誰かに言われてできるようになるものではありません。遊びを通じて実際に泥んこになったり、怪我をしたりするなかで、実感として感じることで「責任」がどういうものかを学ぶわけです。遊びは、体力や発想力、想像力といったものを育てるものでもありますが、もっと「心の奥行き」みたいな部分を深めるものなのだと思います。

写真提供:嶋村仁志
子どもと一緒にリスクを考える
もちろん、「子どもに責任を返す」とはいえ、本当の危険は取り除いてあげないといけません。そこでわたしたちは「リスクとハザード」という考え方を基本にしています。
リスクは、挑戦につきものの危険です。株投資はリスクを伴うものですが、そのリターンはお金ですよね。子どもの遊びの場合、リターンは達成感や友だちと協力した思い出などになるでしょう。それらは大いに味わわせてあげなければなりませんが、一方でハザードという危険もある。
これは、子どもの目には見えない隠れた危険、子どもが自ら選びようがない危険のこと。たとえば、子どもがいかにも走り込みそうな場所にある柱から飛び出ている釘などです。そういったものは、大人がきちんと排除しなければなりません。
また、「リスク・ベネフィット・アセスメント」という考え方もあります。リスクに対してベネフィットとは「利益、効果」といった意味。いわゆるデメリットとメリットと考えてもらったほうがわかりやすいかもしれませんね。
いま、目の前で子どもがある遊びに挑戦しようとしている。それに伴うリスクはどれくらいのものなのか、どんな工夫をすればどれだけ減らせるのか。そして、子ども自身がどれだけ「やりたい」と思っているのか、やったことでどんなものを得られるのか。それらを総合的に判断し、子どもにチャレンジさせるかどうかを決めるのです。
もし、本当にやめたほうがいいものであれば、子どもと話をしながら「今回はあきらめよう」と伝える。ある程度の年齢になれば、子どもでもしっかり話せばわかってくれるものです。本人抜きで大人が一方的に判断するのはやっぱり良くありません。

写真提供:嶋村仁志
遊びを大事にする大人を増やさなければならない
子どもにとっての危険という点では、いまは高まっている時代だと感じますね。それは、危険な場所が増えたというような外因的なものではありません。あるプレーパークで出会った子どもなのですが、段ボール箱に入って、なんと7、8メートルもある急斜面の崖から滑ろうとしていたのです。なぜそんなことをするかといえば、もっと小さい頃から、より軽い危険を伴う経験を積み重ねていないからなんですね。いわゆる「恐怖心」が育っていないのです。
高さの感覚は5歳までに80%が育つのだそうです。公園に登り棒などの遊具があるのも、高さという感覚、高いことが怖いという感覚を育てるためです。でも、そういう感覚を持てないまま中高生になったとしたらどうでしょう? 幼い子どもより力があるだけに、悪ふざけのつもりで命が危険にさらされるようなことをやりかねません。
ところが、いまは子どもからどんどん危険を遠ざける傾向にありますよね。放課後児童クラブなどの子どもを預かる場では、とにかく危なそうなものはすべて「なし!」。「ジャングルジムは2段目まで」「ブランコの立ちこぎは2年生から」といったルールがいくつもある。

これは、雇用の問題も関係しています。職員は嘱託社員やパートなど雇用形態がバラバラですから、子ども教育に対するモチベーションもバラバラ。結果、親御さんからクレームを恐れて、少しでもリスクがあれば「やめておきましょう」ということになってしまうのです。
そんな環境で育った子どもは、チャレンジできないまま体だけが成長し、本当の危険や恐怖を実体験のなかで得ることができない。そうなると、自分の痛みを知らないばかりか、他人の痛みにも共感することができないのです。それは、子ども自身はもちろん、その周囲の人間にとっても危険なことでもあります。
子どもたちだけでしっかり遊べる世のなかであれば、わたしたちのような大人は必要ありません。ただ、これだけ子どもが遊べない社会になると、遊ぶことを大事にできる大人を増やさなければなりませんね。
そして、大人たちには、遊んでいる子どもの表情にぜひしっかり注目する目線を持ってほしい。子どもはなにか面白いものを見つけると、口を開けたまま顔が固まります。これが最大の関心を示している表情なのです。この表情こそ、挑戦したい気持ち、失敗してもへこたれない気持ち、発想力、集中力といった、遊びをとおして得られるものの原点です。その芽生えを見逃してしまうのは、親としてすごくもったいないことですよ。

『子どもの放課後にかかわる人のQ&A50 子どもの力になるプレイワーク実践』
嶋村仁志 他 著/学文社(2017)

■ TOKYO PLAY代表理事・嶋村仁志さん インタビュー一覧
第1回:遊具なし、プログラムなし。異例だらけの“ガラクタ遊び”が欧州で大人気の理由
第2回:大切にしたい遊びの“リスク”。子どものチャレンジを支える遊びのルールとは?
第3回:子どもの工作が“失敗作”でも、親はアドバイスしてはいけない
第4回:中高生では遅い。子どもが体験すべき「小さな危険」と「小さないたずら」
【プロフィール】
嶋村仁志(しまむら・ひとし)
1968年8月6日生まれ、東京都出身。子ども時代は野球と自転車と缶けりざんまいの日々を送る。英国・リーズ・メトロポリタン大学社会健康学部プレイワーク学科高等教育課程修了。1996年に羽根木プレーパークの常駐プレーリーダー職に就いて以降、プレイワーカーとして川崎市子ども夢パーク、プレーパークむさしのなど各地の冒険遊び場のスタッフを歴任。その後フリーランスとなり、国内外の冒険遊び場づくりをサポートしながら、研修や講演会をおこなう。2010年、「すべての子どもが豊かに遊べる東京」をコンセプトにTOKYO PLAYを設立。2005年から2011年までIPA(子どもの遊ぶ権利のための国際協会)東アジア・太平洋地域副代表を務め、現在はTOKYO PLAY代表理事、日本冒険遊び場づくり協会理事、大妻女子大学非常勤講師。
【ライタープロフィール】
清家茂樹(せいけ・しげき)
1975年生まれ、愛媛県出身。出版社勤務を経て2012年に独立し、編集プロダクション・株式会社ESSを設立。ジャンルを問わずさまざまな雑誌・書籍の編集に携わる。